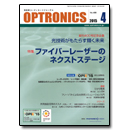☆★☆ 新着情報はRSSで配信しています。★☆★
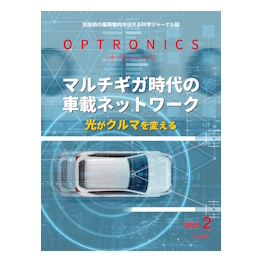
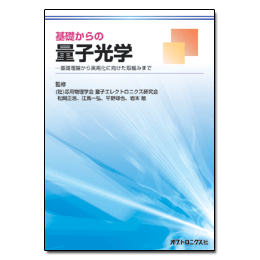
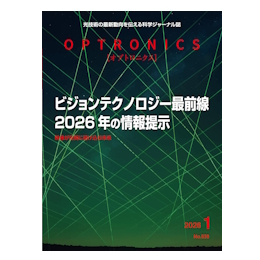
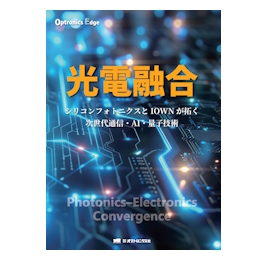 光と電子の特性を融合した「光電融合技術」は、通信をはじめ、AI、量子、センシング分野で革新的な可能性を切り拓いています。
光と電子の特性を融合した「光電融合技術」は、通信をはじめ、AI、量子、センシング分野で革新的な可能性を切り拓いています。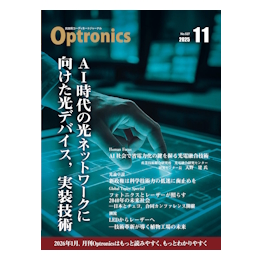
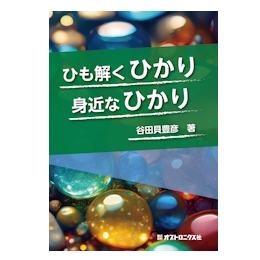 私たちのまわりには、光があふれています。
私たちのまわりには、光があふれています。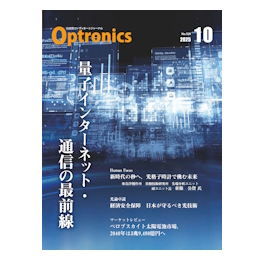
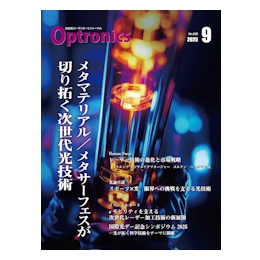
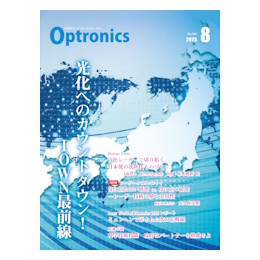
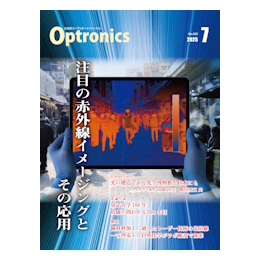
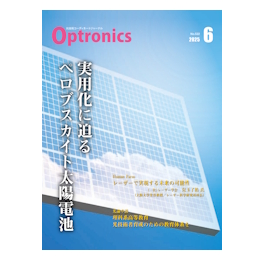
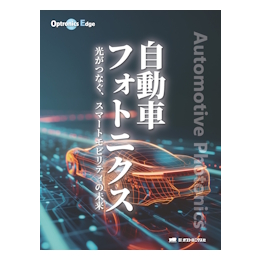
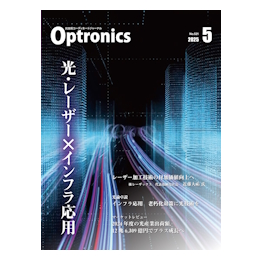
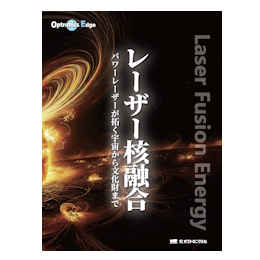
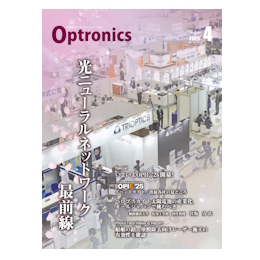
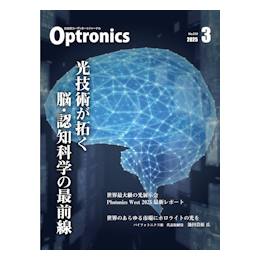
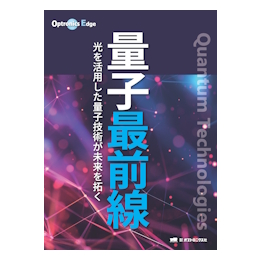
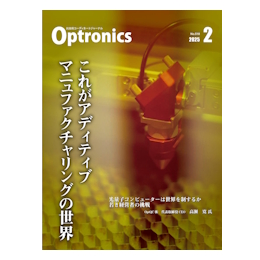
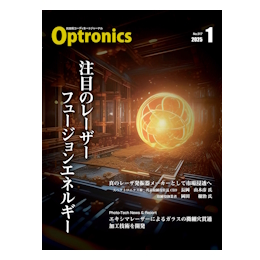
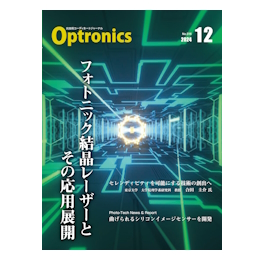
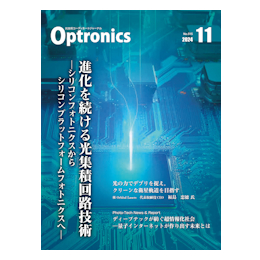
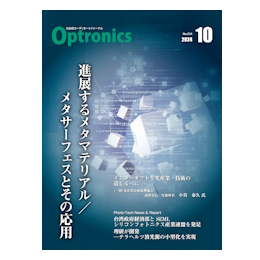
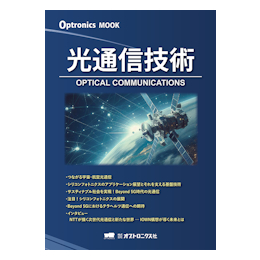
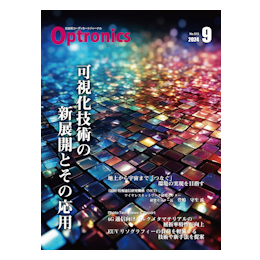
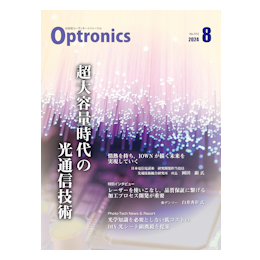
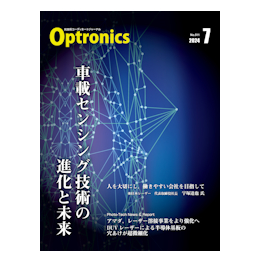 ADAS(先進運転支援システム)や自動運転システムの実現に向けては、センシング技術の高度化が求められています。そのキーとなるのは光技術であり、自動車分野でも応用研究・開発が進んでいます。今回、注目すべき車載用センシング技術を解説します。
ADAS(先進運転支援システム)や自動運転システムの実現に向けては、センシング技術の高度化が求められています。そのキーとなるのは光技術であり、自動車分野でも応用研究・開発が進んでいます。今回、注目すべき車載用センシング技術を解説します。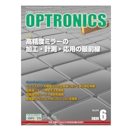 国内にはいくつかの放射光施設が稼働し、学術・産業における研究・開発を支えています。一方で、こうした施設の高度化には先進的な光学技術が導入され、高精度な光デバイスが開発されています。本特集号では実用化が進む、高精度ミラーの加工・計測から応用まで解説していただきました。
国内にはいくつかの放射光施設が稼働し、学術・産業における研究・開発を支えています。一方で、こうした施設の高度化には先進的な光学技術が導入され、高精度な光デバイスが開発されています。本特集号では実用化が進む、高精度ミラーの加工・計測から応用まで解説していただきました。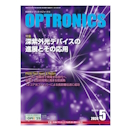 今月号の特集は、日進月歩で進展している深紫外光デバイスです。従来技術と比較して高速応答や低消費電力などのメリットが享受できるため、その実用化が期待されており、今回は高出力・高効率化や短波長化へのアプローチとして材料や構造の開発、さらに光制御といった観点から最新の研究開発を解説していただきました。
今月号の特集は、日進月歩で進展している深紫外光デバイスです。従来技術と比較して高速応答や低消費電力などのメリットが享受できるため、その実用化が期待されており、今回は高出力・高効率化や短波長化へのアプローチとして材料や構造の開発、さらに光制御といった観点から最新の研究開発を解説していただきました。 2024年4月号の特集は、昨年のノーベル物理学賞を受賞したアト秒光パルス生成において、日本が進めてきた高輝度化(高出力化)に向けた研究開発と、期待される応用について解説します。
2024年4月号の特集は、昨年のノーベル物理学賞を受賞したアト秒光パルス生成において、日本が進めてきた高輝度化(高出力化)に向けた研究開発と、期待される応用について解説します。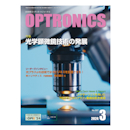 2024年3月号の特集は、東京大学先端科学技術研究センターの小関泰之教授に企画コーディネイトをいただいたもので、光・レーザーによる顕微鏡技術の進展やその応用トピックなどに焦点を当てました。それらの観点より研究・開発を解説していただきます。
2024年3月号の特集は、東京大学先端科学技術研究センターの小関泰之教授に企画コーディネイトをいただいたもので、光・レーザーによる顕微鏡技術の進展やその応用トピックなどに焦点を当てました。それらの観点より研究・開発を解説していただきます。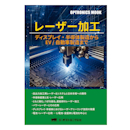 OPTRONICS MOOK第5弾となる「レーザー加工」が刊行されました!月刊オプトロニクスに掲載された業界第一人者の記事を再編集し、ディスプレイ、半導体製造、EV・自動車製造で鍵を握るレーザー加工技術について解説した一冊です。
OPTRONICS MOOK第5弾となる「レーザー加工」が刊行されました!月刊オプトロニクスに掲載された業界第一人者の記事を再編集し、ディスプレイ、半導体製造、EV・自動車製造で鍵を握るレーザー加工技術について解説した一冊です。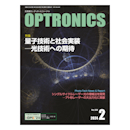 2024年2月号の特集は、量子技術の社会実装を焦点にあてて企画しました。量子コンピュータ、量子暗号通信、量子計測・センシングといった量子科学技術分野の研究・開発の動向に注目が集まっています。とりわけ、これらの技術が社会に実装されていくことが期待されています。
2024年2月号の特集は、量子技術の社会実装を焦点にあてて企画しました。量子コンピュータ、量子暗号通信、量子計測・センシングといった量子科学技術分野の研究・開発の動向に注目が集まっています。とりわけ、これらの技術が社会に実装されていくことが期待されています。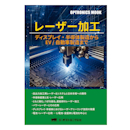 オプトロニクス社最新刊・OPTRONICS MOOK第5弾となる「レーザー加工」の予約受付を開始いたしました。
オプトロニクス社最新刊・OPTRONICS MOOK第5弾となる「レーザー加工」の予約受付を開始いたしました。 2023年8月28日、経済安全保障推進会議・統合イノベーション戦略推進会議において、経済安全保障重要技術育成プログラム第二次研究開発ビジョンがまとめられ、この中に高効率・高品質レーザー加工技術の研究開発の推進が盛り込まれました。革新的な製造技術分野においてレーザー技術がますます注目されることになります。 本号ではレーザー加工技術に焦点を当て、その動向をお届けします。
2023年8月28日、経済安全保障推進会議・統合イノベーション戦略推進会議において、経済安全保障重要技術育成プログラム第二次研究開発ビジョンがまとめられ、この中に高効率・高品質レーザー加工技術の研究開発の推進が盛り込まれました。革新的な製造技術分野においてレーザー技術がますます注目されることになります。 本号ではレーザー加工技術に焦点を当て、その動向をお届けします。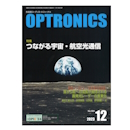 宇宙開発はいま大きな注目を集めており、様々なインフラ開発が進んでいます。通信分野もその一つで、今月の特集では宇宙における光通信技術をメインテーマに、第一線で活躍されている方々に解説していただきました。
宇宙開発はいま大きな注目を集めており、様々なインフラ開発が進んでいます。通信分野もその一つで、今月の特集では宇宙における光通信技術をメインテーマに、第一線で活躍されている方々に解説していただきました。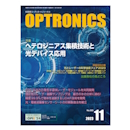 機能性材料を集積する技術が大きく進展しています。半導体分野でも注目されており、ヘテロジニアス集積技術としてその応用が取り組まれています。異種の機能性材料やデバイスを一つに集積するためには熱影響も考慮しなければいけません。本号ではヘテロジニアス集積技術と光デバイス応用に着目し、最新の研究・開発動向に迫ります。
機能性材料を集積する技術が大きく進展しています。半導体分野でも注目されており、ヘテロジニアス集積技術としてその応用が取り組まれています。異種の機能性材料やデバイスを一つに集積するためには熱影響も考慮しなければいけません。本号ではヘテロジニアス集積技術と光デバイス応用に着目し、最新の研究・開発動向に迫ります。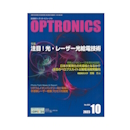 電力の無線給電技術に注目が集まっています。これを光・レーザーを用いると、どのようなメリットがあるのでしょうか? 10 月号特集ではそこに迫るもので、光ファイバーによる給電を含めた技術に焦点を当て、その研究開発を解説していただきます。
電力の無線給電技術に注目が集まっています。これを光・レーザーを用いると、どのようなメリットがあるのでしょうか? 10 月号特集ではそこに迫るもので、光ファイバーによる給電を含めた技術に焦点を当て、その研究開発を解説していただきます。 メタマテリアル / メタサーフェスの実用展開が期待されています。メタマテリアルとは人工的な物質であり、その構造体によって様々な機能を発現させることが可能になります。今回、常識を 覆すような応用を中心とした特集を企画しました。
メタマテリアル / メタサーフェスの実用展開が期待されています。メタマテリアルとは人工的な物質であり、その構造体によって様々な機能を発現させることが可能になります。今回、常識を 覆すような応用を中心とした特集を企画しました。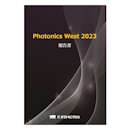 3年ぶりに復活!本書は渡米された皆様のご尽力のもと、LASE、OPTO、BiOSの3つの学術会議のレポートと、展示会レポートを収録しています。フォトニクス関連分野は、今後も産業界や学術界にとってますます重要な研究・開発分野になると予想されます。ぜひこの機会にお申し込みください。
3年ぶりに復活!本書は渡米された皆様のご尽力のもと、LASE、OPTO、BiOSの3つの学術会議のレポートと、展示会レポートを収録しています。フォトニクス関連分野は、今後も産業界や学術界にとってますます重要な研究・開発分野になると予想されます。ぜひこの機会にお申し込みください。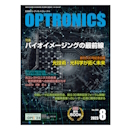 おかげさまで月刊オプトロニクスは創刊500号を迎えることができました。500号記念企画として2014年に青色発光ダイオード研究でノーベル物理学賞を受賞された名古屋大学・天野浩先生のインタビューを掲載しました。また、「光技術・光科学が拓く未来」をテーマに、今後注目すべき分野を選出し、研究開発を主導されている方々にコメントを寄せていただきました。特集は、名古屋大学の西澤典彦先生に企画コーディネートいただいた「バイオイメージングの最前線」です。ぜひご覧ください。
おかげさまで月刊オプトロニクスは創刊500号を迎えることができました。500号記念企画として2014年に青色発光ダイオード研究でノーベル物理学賞を受賞された名古屋大学・天野浩先生のインタビューを掲載しました。また、「光技術・光科学が拓く未来」をテーマに、今後注目すべき分野を選出し、研究開発を主導されている方々にコメントを寄せていただきました。特集は、名古屋大学の西澤典彦先生に企画コーディネートいただいた「バイオイメージングの最前線」です。ぜひご覧ください。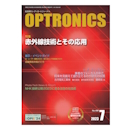 今月号の特集では、赤外線波長領域における光源・デバイスからシステムに焦点を当て、産学より注目の技術・開発を解説していただきました。
今月号の特集では、赤外線波長領域における光源・デバイスからシステムに焦点を当て、産学より注目の技術・開発を解説していただきました。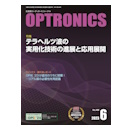 本特集では、多彩な応用に注目の集まるテラヘルツ波技術の実用的な可能性を探ります。様々な分野での可視化を実現する量子カスケードレーザー、ホトマルの光源・検出器をはじめ、テラヘルツイメージングに関する応用分野を紹介し、テラヘルツ波の更なる発展を模索します。
本特集では、多彩な応用に注目の集まるテラヘルツ波技術の実用的な可能性を探ります。様々な分野での可視化を実現する量子カスケードレーザー、ホトマルの光源・検出器をはじめ、テラヘルツイメージングに関する応用分野を紹介し、テラヘルツ波の更なる発展を模索します。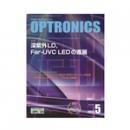 今月号の特集は、紫外線光源・技術に焦点を当て、UVC 半導体レーザーの室温連続発振や,人体に影響がないとされるUV 波長帯光源,さらに高出力化に向けた技術などのさらに進んだ研究開発について解説いただきました。紫外線の、特に280nm以下の波長域がウイルス不活化に有効とされ注目を集めましたが、それ以外にもバイオメディカルや加工などへの応用も見込まれており、期待が高まっています。
今月号の特集は、紫外線光源・技術に焦点を当て、UVC 半導体レーザーの室温連続発振や,人体に影響がないとされるUV 波長帯光源,さらに高出力化に向けた技術などのさらに進んだ研究開発について解説いただきました。紫外線の、特に280nm以下の波長域がウイルス不活化に有効とされ注目を集めましたが、それ以外にもバイオメディカルや加工などへの応用も見込まれており、期待が高まっています。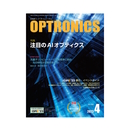 今、AI による光学技術が注目されています。本号では大阪大学大学院情報科学研究科・教授の谷田 純氏にご協力をいただき、AI オプティクスを切り口とした特集を企画しました。
今、AI による光学技術が注目されています。本号では大阪大学大学院情報科学研究科・教授の谷田 純氏にご協力をいただき、AI オプティクスを切り口とした特集を企画しました。 3月号の特集では、光通信だけでなく、ヘルスケアやLIDARなどのセンシングへの応用、光AIや量子演算などの革新的な演算処理回路への応用も期待される、シリコンフォトニクス技術の研究開発動向を解説していただきました。
3月号の特集では、光通信だけでなく、ヘルスケアやLIDARなどのセンシングへの応用、光AIや量子演算などの革新的な演算処理回路への応用も期待される、シリコンフォトニクス技術の研究開発動向を解説していただきました。 幅広い分野において利活用が進むセンサーは、様々な種類が開発されています。昨今では光・量 子技術を活用したセンサーの研究・開発も進んでおり、これまで以上に高度な計測・センシングにつながることが期待されています。そこで2月号では『光・量子計測・センシング』の最先端研究に着目し、特集を企画しました。
幅広い分野において利活用が進むセンサーは、様々な種類が開発されています。昨今では光・量 子技術を活用したセンサーの研究・開発も進んでおり、これまで以上に高度な計測・センシングにつながることが期待されています。そこで2月号では『光・量子計測・センシング』の最先端研究に着目し、特集を企画しました。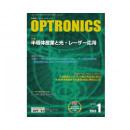 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 月刊オプトロニクスの連載をまとめた「光エレクトロニクスのシミュレーション技術」に書籍版が登場!光エレクトロニクスデバイスの特性解析、設計に関するシミュレーション技術を解説。実際にシミュレーションが体験できる付録も充実!
月刊オプトロニクスの連載をまとめた「光エレクトロニクスのシミュレーション技術」に書籍版が登場!光エレクトロニクスデバイスの特性解析、設計に関するシミュレーション技術を解説。実際にシミュレーションが体験できる付録も充実!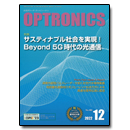 サスティナブルな社会の実現にはテクノロジーの活用が謳われており、通信技術もそれを支える重要な基盤技術と言われています。要となる光通信は Beyond 5G対応によりそのアプリケーションが広がっており、高速・大容量化はもとより、無線通信においても光化が注目されています。
サスティナブルな社会の実現にはテクノロジーの活用が謳われており、通信技術もそれを支える重要な基盤技術と言われています。要となる光通信は Beyond 5G対応によりそのアプリケーションが広がっており、高速・大容量化はもとより、無線通信においても光化が注目されています。 本特集では医療、エネルギー、モビリティ、ディスプレイ、生活、フロンティア領域などの分野において光技術がどのように貢献できるかをテーマに注目される研究・開発を解説していただきます。
本特集では医療、エネルギー、モビリティ、ディスプレイ、生活、フロンティア領域などの分野において光技術がどのように貢献できるかをテーマに注目される研究・開発を解説していただきます。 10月17日刊行いたしました!超スマート社会(「Society 5.0」)の実現のために必要不可欠な「センサ&センシング技術」について、その中でも現在特に重要かつ注目を集めている光センサとイメージセンサ、およびそれらを使ったセンシング技術をまとめた資料集が登場!デバイスからシステム、アプリケーションまでを幅広く収録した、光センサとイメージセンサに関するバイブルとなっています。
10月17日刊行いたしました!超スマート社会(「Society 5.0」)の実現のために必要不可欠な「センサ&センシング技術」について、その中でも現在特に重要かつ注目を集めている光センサとイメージセンサ、およびそれらを使ったセンシング技術をまとめた資料集が登場!デバイスからシステム、アプリケーションまでを幅広く収録した、光センサとイメージセンサに関するバイブルとなっています。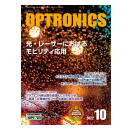 自動運転などスマートモビリティの実現において、光・レーザー技術の重要性が増しています。昨今では空飛ぶモビリティへの応用に向けた光デバイス開発プロジェクトもスタートし、関心を集めています。月刊オプトロニクスではこれまでもモビリティ応用に関する特集を企画してきましたが、本号ではより広範にわたるモビリティ分野を支える光技術のトピックを集めました。
自動運転などスマートモビリティの実現において、光・レーザー技術の重要性が増しています。昨今では空飛ぶモビリティへの応用に向けた光デバイス開発プロジェクトもスタートし、関心を集めています。月刊オプトロニクスではこれまでもモビリティ応用に関する特集を企画してきましたが、本号ではより広範にわたるモビリティ分野を支える光技術のトピックを集めました。 1977年3月22日に伊賀健一東工大名誉教授・元学長が面発光レーザーを発案されてから45年が経ち、いまや面発光レーザーは情報通信機器からスマートフォンなど様々な機器に採用されています。
1977年3月22日に伊賀健一東工大名誉教授・元学長が面発光レーザーを発案されてから45年が経ち、いまや面発光レーザーは情報通信機器からスマートフォンなど様々な機器に採用されています。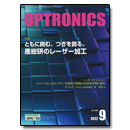 例年、本誌 9 月号では国内の大学や研究機関における光の研究に焦点を当て、特集を企画してきましたが、本号では『産業技術総合研究所のレーザー加工・計測』にスポットライトを当て、次世代ものづくりの解説をしていただきます。サイバーフィジカルシステム実現によるレーザー加工の進展が注目されています。
例年、本誌 9 月号では国内の大学や研究機関における光の研究に焦点を当て、特集を企画してきましたが、本号では『産業技術総合研究所のレーザー加工・計測』にスポットライトを当て、次世代ものづくりの解説をしていただきます。サイバーフィジカルシステム実現によるレーザー加工の進展が注目されています。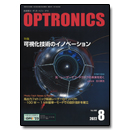 光・レーザーによる計測・イメージング技術は、様々な分野で採用が進んでおり、さらなる技術開発によって進展しています。今月号では光・レーザーによる『見えないものを視る技術』として特集を企画。それぞれのキーパーソンの方々に解説をしていただきます。
光・レーザーによる計測・イメージング技術は、様々な分野で採用が進んでおり、さらなる技術開発によって進展しています。今月号では光・レーザーによる『見えないものを視る技術』として特集を企画。それぞれのキーパーソンの方々に解説をしていただきます。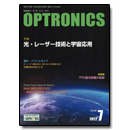 宇宙インフラ開発において光・レーザー技術が求められています。スペースデブリ除去、地球・宇宙観測、資源探索、衛星間通信など、さらには光格子時計の宇宙応用も始まろうとしています。これらに不可欠とされているのが、光・レーザーです。本号では特に注目の光・レーザー技術における宇宙応用研究・開発にスポットを当て解説していただきます。
宇宙インフラ開発において光・レーザー技術が求められています。スペースデブリ除去、地球・宇宙観測、資源探索、衛星間通信など、さらには光格子時計の宇宙応用も始まろうとしています。これらに不可欠とされているのが、光・レーザーです。本号では特に注目の光・レーザー技術における宇宙応用研究・開発にスポットを当て解説していただきます。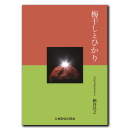 月刊オプトロニクスで好評連載中の「ひかりがたり」が単行本化!
月刊オプトロニクスで好評連載中の「ひかりがたり」が単行本化!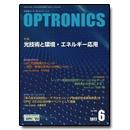 本号の特集は「光と環境・エネルギー」に着目し、気象、地球温暖化排出ガスなどのモニタリングに関し、如何に光・レーザー技術が貢献できるかの視点で企画、解説していただきました。
本号の特集は「光と環境・エネルギー」に着目し、気象、地球温暖化排出ガスなどのモニタリングに関し、如何に光・レーザー技術が貢献できるかの視点で企画、解説していただきました。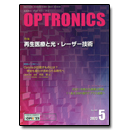 健康長寿社会の実現において、再生医療の実用化が注目されています。本特集号では 再生医療を支える光・レーザー技術に焦点を当て、最新の研究を解説していただきます。
健康長寿社会の実現において、再生医療の実用化が注目されています。本特集号では 再生医療を支える光・レーザー技術に焦点を当て、最新の研究を解説していただきます。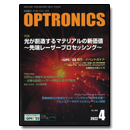 今回は先進レーザープロセッシングに焦点を当て、レーザー加工による材料の新たな価値を生み出す可能性の高い技術で構成しました。「光が創造するマテリアルの新価値」に着目し、レーザー光と物質の相互作用を利用しマテリアルの高付加価値化を狙う先端レーザープロセッシング技術について紹介します。
今回は先進レーザープロセッシングに焦点を当て、レーザー加工による材料の新たな価値を生み出す可能性の高い技術で構成しました。「光が創造するマテリアルの新価値」に着目し、レーザー光と物質の相互作用を利用しマテリアルの高付加価値化を狙う先端レーザープロセッシング技術について紹介します。 エネルギーの消費による地球温暖化対策のルール化が推し進められようとしています。光・レーザーデバイスや応用製品に対しても低消費電力化の要求はますます厳しくなることが予測されています。この対応の一つとして、シリコンフォトニクスが注目されています。3 月号では、シリコンフォトニクスの新展開を切り口にその研究・開発を先導するエキスパートの方々に解説をお願いしました。
エネルギーの消費による地球温暖化対策のルール化が推し進められようとしています。光・レーザーデバイスや応用製品に対しても低消費電力化の要求はますます厳しくなることが予測されています。この対応の一つとして、シリコンフォトニクスが注目されています。3 月号では、シリコンフォトニクスの新展開を切り口にその研究・開発を先導するエキスパートの方々に解説をお願いしました。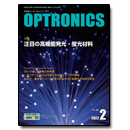 月刊オプトロニクス2月号の特集は『高機能発光・蛍光材料』に焦点を当て、これらの材料を用いた高性能レーザー光源から量子デバイス・システムの実現に向けた研究開発を解説します。
月刊オプトロニクス2月号の特集は『高機能発光・蛍光材料』に焦点を当て、これらの材料を用いた高性能レーザー光源から量子デバイス・システムの実現に向けた研究開発を解説します。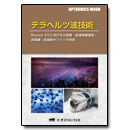 OPTRONICS MOOK 第4弾「テラヘルツ波技術」好評発売中です。Beyond 5Gにおける大容量・高速無線通信や非破壊・非接触センシング技術を中心に、月刊オプトロニクスやOPTRONICS ONLINEに掲載された記事を再編集して掲載しています。
OPTRONICS MOOK 第4弾「テラヘルツ波技術」好評発売中です。Beyond 5Gにおける大容量・高速無線通信や非破壊・非接触センシング技術を中心に、月刊オプトロニクスやOPTRONICS ONLINEに掲載された記事を再編集して掲載しています。 1月号の特集は『パワーレーザーとその応用』です。パワーレーザーとしては、一つにはレーザー核融合が想起されますが、この実現において様々な産業への応用展開も考えられ、加工や資源探査、材料開発などに至る広範にわたります。レーザー核融合研究では、その過程において水素製造があり、カーボンニュートラル実現への貢献が期待されています。ロードマップによれば、2050年にもレーザー核融合発電の商業試験装置の実現が示されています。様々な要素技術が開発され、さらなる技術の波及効果によって多くの社会課題が解決されていくことに期待が寄せられています。
1月号の特集は『パワーレーザーとその応用』です。パワーレーザーとしては、一つにはレーザー核融合が想起されますが、この実現において様々な産業への応用展開も考えられ、加工や資源探査、材料開発などに至る広範にわたります。レーザー核融合研究では、その過程において水素製造があり、カーボンニュートラル実現への貢献が期待されています。ロードマップによれば、2050年にもレーザー核融合発電の商業試験装置の実現が示されています。様々な要素技術が開発され、さらなる技術の波及効果によって多くの社会課題が解決されていくことに期待が寄せられています。 12月号の特集は「バイオイメージング極秘ファイル」です。本特集は、光イメージング法により生物学や医学分野に画期的な高速計測技術の実現をもたらし、斯界のフロントランナーとして活躍する東京大学の合田圭介先生にコーディネイトをいただいたもので、バイオメディカル分野におけるイメージング研究を解説します。
12月号の特集は「バイオイメージング極秘ファイル」です。本特集は、光イメージング法により生物学や医学分野に画期的な高速計測技術の実現をもたらし、斯界のフロントランナーとして活躍する東京大学の合田圭介先生にコーディネイトをいただいたもので、バイオメディカル分野におけるイメージング研究を解説します。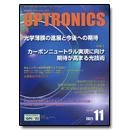 今月の特集は展示会『光とレーザーの科学技術フェア』と連動し、二本企画いたしました。
今月の特集は展示会『光とレーザーの科学技術フェア』と連動し、二本企画いたしました。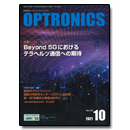 次世代の無線通信の高速・大容量化技術の一つとして、光と電波の間に位置するテラヘルツ波の周波数帯域の活用が検討されています。既に5Gの商用化が開始され、開発の検討は6G/7Gへと移っていますが、4K/8K 等の超高精細映像や VR/AR の普及によって通信容量不足が前倒しされている中にあって、早期の対応が求められています。無線通信のテラヘルツ波の利活用に向けた開発は今後本格的に進むと見られていますが、本特集ではテラヘルツ無線通信のネットワーク・システムの全体像(構想)を紹介するとともに、その実現化技術(デバイス)に焦点をあて、さらに開発に不可欠な測定器も取り上げます。
次世代の無線通信の高速・大容量化技術の一つとして、光と電波の間に位置するテラヘルツ波の周波数帯域の活用が検討されています。既に5Gの商用化が開始され、開発の検討は6G/7Gへと移っていますが、4K/8K 等の超高精細映像や VR/AR の普及によって通信容量不足が前倒しされている中にあって、早期の対応が求められています。無線通信のテラヘルツ波の利活用に向けた開発は今後本格的に進むと見られていますが、本特集ではテラヘルツ無線通信のネットワーク・システムの全体像(構想)を紹介するとともに、その実現化技術(デバイス)に焦点をあて、さらに開発に不可欠な測定器も取り上げます。 本特集では内閣府戦略イノベーション創造プログラム(SIP)の『光・量子を活用した Society5.0 実現化技術』に焦点を当てました。本プログラムの推進体制から具体的な研究・開発、出口戦略などを紹介します。我が国の第5期科学技術基本計画に光・量子技術の重要性が謳われていますが、今回関係機関の全面的なご協力の下、本特集企画を実現することができました。
本特集では内閣府戦略イノベーション創造プログラム(SIP)の『光・量子を活用した Society5.0 実現化技術』に焦点を当てました。本プログラムの推進体制から具体的な研究・開発、出口戦略などを紹介します。我が国の第5期科学技術基本計画に光・量子技術の重要性が謳われていますが、今回関係機関の全面的なご協力の下、本特集企画を実現することができました。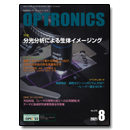 分光計測の活用シーンは広く、様々な産業分野で実用化されていますが、計測対象物の開発に伴い、新たな計測手法が求められるのもこの分野の特長とも言えます。現在、生体応用が注目されており、光によるイメージング技術の高度化が図られています。そこで、8 月号では分光分析による生体イメージングと題する特集を企画しました。分光の基礎から生体イメージング応用まで、その研究開発を解説します。
分光計測の活用シーンは広く、様々な産業分野で実用化されていますが、計測対象物の開発に伴い、新たな計測手法が求められるのもこの分野の特長とも言えます。現在、生体応用が注目されており、光によるイメージング技術の高度化が図られています。そこで、8 月号では分光分析による生体イメージングと題する特集を企画しました。分光の基礎から生体イメージング応用まで、その研究開発を解説します。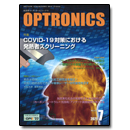 新型コロナウイルス感染の収束が見えない中で、感染状況の把握や予防対策が求められています。光技術が如何にして感染予防対策に寄与できるかに注目されていますが、今回は赤外線技術を活用した体表面温度の実際について特集します。
新型コロナウイルス感染の収束が見えない中で、感染状況の把握や予防対策が求められています。光技術が如何にして感染予防対策に寄与できるかに注目されていますが、今回は赤外線技術を活用した体表面温度の実際について特集します。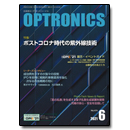 新型コロナ感染拡大を如何に封じ込めるかが喫緊の課題となっていますが、こうした細菌・ウイルスの不活化技術が注目されています。その一つとして期待されているのが、紫外線です。その研究・開発が活発化していますが、6 月号特集では『ポストコロナ時代の紫外線技術』と題し、紫外線による細菌・ウイルス不活化の有用性から光源・装置開発に至るトピックを解説していただきます。
新型コロナ感染拡大を如何に封じ込めるかが喫緊の課題となっていますが、こうした細菌・ウイルスの不活化技術が注目されています。その一つとして期待されているのが、紫外線です。その研究・開発が活発化していますが、6 月号特集では『ポストコロナ時代の紫外線技術』と題し、紫外線による細菌・ウイルス不活化の有用性から光源・装置開発に至るトピックを解説していただきます。 月刊 OPTRONICS 5 月号ではディスプレイ・半導体分野におけるレーザーアニーリング技術の発展に焦点を当てました。この技術分野ではエキシマレーザーに加え、可視光レーザーによるプロセス開発も進んでいます。本特集ではディスプレイはもとより、パワー半導体向けレーザーアニーリング技術も解説します。
月刊 OPTRONICS 5 月号ではディスプレイ・半導体分野におけるレーザーアニーリング技術の発展に焦点を当てました。この技術分野ではエキシマレーザーに加え、可視光レーザーによるプロセス開発も進んでいます。本特集ではディスプレイはもとより、パワー半導体向けレーザーアニーリング技術も解説します。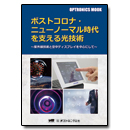 新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見えない中、感染対策が喫緊の
新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見えない中、感染対策が喫緊の 月刊オプトロニクス2021年3月号と4月号の特集では、2020年度まで続けられてきたNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクト『高輝度・高効率次世代レーザー技術開発』のうち、深紫外・超短パルスレーザーから高出力長短波長レーザー、加工プラットフォームに焦点を当て、その成果を解説します。このプロジェクト成果はOPIE21で出展が予定されており、本特集号も会場での配布を予定しています。
月刊オプトロニクス2021年3月号と4月号の特集では、2020年度まで続けられてきたNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクト『高輝度・高効率次世代レーザー技術開発』のうち、深紫外・超短パルスレーザーから高出力長短波長レーザー、加工プラットフォームに焦点を当て、その成果を解説します。このプロジェクト成果はOPIE21で出展が予定されており、本特集号も会場での配布を予定しています。 月刊オプトロニクス2021年3月号と4月号の特集では、2020年度まで続けられてきたNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクト『高輝度・高効率次世代レーザー技術開発』のうち、深紫外・超短パルスレーザーから高出力長短波長レーザー、加工プラットフォームに焦点を当て、その成果を解説します。このプロジェクト成果はOPIE21で出展が予定されており、本特集号も会場での配布を予定しています。
月刊オプトロニクス2021年3月号と4月号の特集では、2020年度まで続けられてきたNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクト『高輝度・高効率次世代レーザー技術開発』のうち、深紫外・超短パルスレーザーから高出力長短波長レーザー、加工プラットフォームに焦点を当て、その成果を解説します。このプロジェクト成果はOPIE21で出展が予定されており、本特集号も会場での配布を予定しています。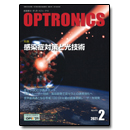

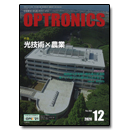
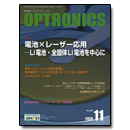
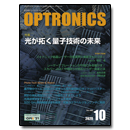
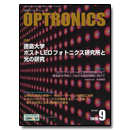
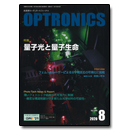

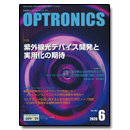
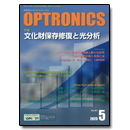
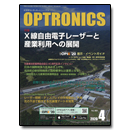

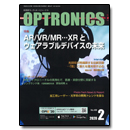
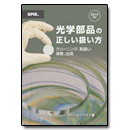

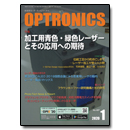



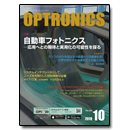



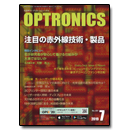

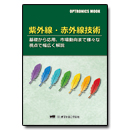 OPTRONICS MOOKに第2弾として「紫外線・赤外線技術」が登場!
OPTRONICS MOOKに第2弾として「紫外線・赤外線技術」が登場!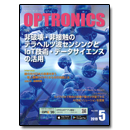 2019 年5 月号特集は、テラヘルツ波センシングに焦点を当てました。テラヘルツ波センシングが様々な産業分野に導入され、さらにIoT 技術を活用することで高度な定量化が期待されています。
2019 年5 月号特集は、テラヘルツ波センシングに焦点を当てました。テラヘルツ波センシングが様々な産業分野に導入され、さらにIoT 技術を活用することで高度な定量化が期待されています。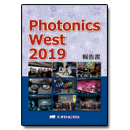 本報告書ではLASE、OPTO、BIOSの3つの学術会議レポートと、展示会レポートで構成されています。
本報告書ではLASE、OPTO、BIOSの3つの学術会議レポートと、展示会レポートで構成されています。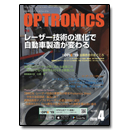 自動運転が注目を浴びる自動車業界ですが、製造分野でも大きな変革が起きています。CFRP などの材料への対応やEV 化に伴う製造プロセスの確立ですが、ボティ、エンジン、バッテリーや電装品の加工にはレーザーの採用が進んでいます。今回の特集は自動車製造におけるレーザー加工に焦点を当てました。
自動運転が注目を浴びる自動車業界ですが、製造分野でも大きな変革が起きています。CFRP などの材料への対応やEV 化に伴う製造プロセスの確立ですが、ボティ、エンジン、バッテリーや電装品の加工にはレーザーの採用が進んでいます。今回の特集は自動車製造におけるレーザー加工に焦点を当てました。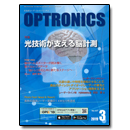 3月号は光技術が支える脳機能計測技術にスポットライトを当てました。脳の解明やその活動の仕組みを理解することは、健康を維持するためにも重要です。 そこには光・レーザーが果たす役割も大きなものがあります。研究・開発の発展、促進につながる製品が求められています。
3月号は光技術が支える脳機能計測技術にスポットライトを当てました。脳の解明やその活動の仕組みを理解することは、健康を維持するためにも重要です。 そこには光・レーザーが果たす役割も大きなものがあります。研究・開発の発展、促進につながる製品が求められています。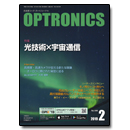 近年、100Gbpsのキャパシティを超えるKa帯ブロードバンド衛星通信や、GoogleやFacebookを中心に、Space-X、Oneweb、O3b、Leosat、eightyLEO等、多数の小型衛星群や無人航空機群を用いたメガコンステレーション計画が世界各国で打ち出され、超高速な光通信を用いた衛星計画が台頭してきています。これらの計画は、従来の宇宙開発そのものを革新する可能性があります。変化の速いこの分野の情勢の中で、日本における光技術を用いた宇宙通信分野の研究開発について、具体的に動きのあるプロジェクトや利活用動向について解説します。
近年、100Gbpsのキャパシティを超えるKa帯ブロードバンド衛星通信や、GoogleやFacebookを中心に、Space-X、Oneweb、O3b、Leosat、eightyLEO等、多数の小型衛星群や無人航空機群を用いたメガコンステレーション計画が世界各国で打ち出され、超高速な光通信を用いた衛星計画が台頭してきています。これらの計画は、従来の宇宙開発そのものを革新する可能性があります。変化の速いこの分野の情勢の中で、日本における光技術を用いた宇宙通信分野の研究開発について、具体的に動きのあるプロジェクトや利活用動向について解説します。 あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。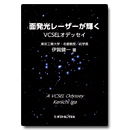 2018年12月14日刊行いたしました!
2018年12月14日刊行いたしました!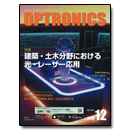 12月号特集では,土木・建築分野における光・レーザー応用技術に焦点を当てます。この中でインフラ計測や建造物のメンテナンスに関わる技術を解説します。この分野では光・レーザーの特性を活かすことで従来技術と比較して速度や工程数の削減など優位性があると考えられています。しかし、開発は発展途上です。レーザーはもとより、光学系など各種デバイス・システムの性能向上が実用化のカギを握っています。
12月号特集では,土木・建築分野における光・レーザー応用技術に焦点を当てます。この中でインフラ計測や建造物のメンテナンスに関わる技術を解説します。この分野では光・レーザーの特性を活かすことで従来技術と比較して速度や工程数の削減など優位性があると考えられています。しかし、開発は発展途上です。レーザーはもとより、光学系など各種デバイス・システムの性能向上が実用化のカギを握っています。 プロジェクトとして、総務省委託事業でテラヘルツ波周波数帯の通信技術の研究開発が進んでいます。実用化に向けて標準化やロードマップをNICT が主導。研究開発ではテラヘルツ波発生と通信応用に向けた各アプローチによるデバイス開発が行なわれています。今回の特集ではテラヘルツ波無線通信技術を取り上げます。
プロジェクトとして、総務省委託事業でテラヘルツ波周波数帯の通信技術の研究開発が進んでいます。実用化に向けて標準化やロードマップをNICT が主導。研究開発ではテラヘルツ波発生と通信応用に向けた各アプローチによるデバイス開発が行なわれています。今回の特集ではテラヘルツ波無線通信技術を取り上げます。 2015年2月号で特集してから約3年。我が国の人工光合成とソーラー水素製造技術はどこまで進展しているのでしょうか。今回、そこに焦点を当てています。実用化には人工光合成の高効率化と太陽光発電との融合がカギを握ると言われていますが、その一端をお届けします。
2015年2月号で特集してから約3年。我が国の人工光合成とソーラー水素製造技術はどこまで進展しているのでしょうか。今回、そこに焦点を当てています。実用化には人工光合成の高効率化と太陽光発電との融合がカギを握ると言われていますが、その一端をお届けします。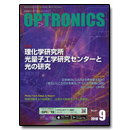 2018年4月に理化学研究所の光量子工学研究領域が、「光量子工学研究センター」に変わりました。そこで今回、光量子工学研究センターにおける、その役割といくつかの光の研究活動を取り上げます。
2018年4月に理化学研究所の光量子工学研究領域が、「光量子工学研究センター」に変わりました。そこで今回、光量子工学研究センターにおける、その役割といくつかの光の研究活動を取り上げます。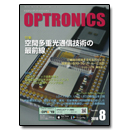 8月号特集は、空間多重光通信技術の研究・開発に焦点を当てました。本誌では5年ぶりの企画となりますが、その間に大きな進展がありました。大容量光ファイバーネットワークの将来を担う空間多重光通信技術について、光ファイバー、コンポーネント、システムに大別してその開発の現状と今後を詳説します。
8月号特集は、空間多重光通信技術の研究・開発に焦点を当てました。本誌では5年ぶりの企画となりますが、その間に大きな進展がありました。大容量光ファイバーネットワークの将来を担う空間多重光通信技術について、光ファイバー、コンポーネント、システムに大別してその開発の現状と今後を詳説します。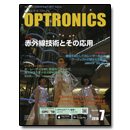 7月号特集は「赤外線技術とその応用」です。広範にわたる赤外線技術のトピックを、基礎と応用を中心に解説します。さらに赤外線技術以外の技術の動向にも触れる内容となることから、技術比較という観点でも有益な情報を提供します。
7月号特集は「赤外線技術とその応用」です。広範にわたる赤外線技術のトピックを、基礎と応用を中心に解説します。さらに赤外線技術以外の技術の動向にも触れる内容となることから、技術比較という観点でも有益な情報を提供します。 6月号特集は,『ウェアラブルとVR/ARの光学系』をテーマとしています。網膜走査型のレーザーメガネが商品化され,この分野は注目度を増しています。また,光学技術の進展によってさらにウェアラブル型メガネは小型・軽量化へと進むものと見られています。その要素技術や画像補正技術などを解説します。
6月号特集は,『ウェアラブルとVR/ARの光学系』をテーマとしています。網膜走査型のレーザーメガネが商品化され,この分野は注目度を増しています。また,光学技術の進展によってさらにウェアラブル型メガネは小型・軽量化へと進むものと見られています。その要素技術や画像補正技術などを解説します。  自動車分野における自動運転実現のための開発に注目が集まっています。その実現には光技術が不可欠とされ,様々なアプローチによって研究・開発が活発化しています。
自動車分野における自動運転実現のための開発に注目が集まっています。その実現には光技術が不可欠とされ,様々なアプローチによって研究・開発が活発化しています。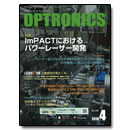 2018年4月号特集は,内閣府の革新的研究開発推進プログラムが推進する研究開発の一つ,「ユビキタス・パワーレーザーによる安全・安心・長寿命社会の実現」に焦点を当て、パワーレーザーの開発と産業化の行方を解説します。このプログラムでは,レーザーの小型化と,新たなアプリケーションの創出を目指し,研究・開発が進んでいます。いま、その開発はどこまで来たかを紹介します。
2018年4月号特集は,内閣府の革新的研究開発推進プログラムが推進する研究開発の一つ,「ユビキタス・パワーレーザーによる安全・安心・長寿命社会の実現」に焦点を当て、パワーレーザーの開発と産業化の行方を解説します。このプログラムでは,レーザーの小型化と,新たなアプリケーションの創出を目指し,研究・開発が進んでいます。いま、その開発はどこまで来たかを紹介します。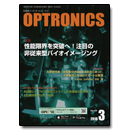 イメージング技術の進化には目覚ましいものがあります。多種多様な対象物の可視化向けに様々な顕微手法が開発されていますが、2018 年3 月号では従来型のイメージング手法ではなく,革新的なイメージング手法,いわゆる非従来型イメージングに焦点を当てます。深部イメージングやレンズレスイメージング,高速イメージング,ラベルフリーイメージングなど,その研究開発の動向を解説します。
イメージング技術の進化には目覚ましいものがあります。多種多様な対象物の可視化向けに様々な顕微手法が開発されていますが、2018 年3 月号では従来型のイメージング手法ではなく,革新的なイメージング手法,いわゆる非従来型イメージングに焦点を当てます。深部イメージングやレンズレスイメージング,高速イメージング,ラベルフリーイメージングなど,その研究開発の動向を解説します。 最新アップデート版!
最新アップデート版! 2018年2月号特集は,紫色・紫外光源技術に焦点を当てました。目にやさしいと言われる紫色光源,さらに深紫外領域における光源,最先端リソグラフィー用EUV 光源,それに紫外レーザー加工技術を解説します。題して「紫色・紫外光源技術のインパクト」です。
2018年2月号特集は,紫色・紫外光源技術に焦点を当てました。目にやさしいと言われる紫色光源,さらに深紫外領域における光源,最先端リソグラフィー用EUV 光源,それに紫外レーザー加工技術を解説します。題して「紫色・紫外光源技術のインパクト」です。 2018年1月号特集は、レーザーによって機能性を有する材料作製を可能にする技術に焦点を当てました。キーワードは、レーザーによる転写(パターニング&コーティング)です。材料の進化が新たな製品の創出につながる可能性があります。その作製プロセスとしてレーザーの応用が期待されています。
2018年1月号特集は、レーザーによって機能性を有する材料作製を可能にする技術に焦点を当てました。キーワードは、レーザーによる転写(パターニング&コーティング)です。材料の進化が新たな製品の創出につながる可能性があります。その作製プロセスとしてレーザーの応用が期待されています。 月刊 OPTRONICS 12 月号の特集は,光技術がもたらすロボット開発の可能性を探ります。医療,農・林業,災害対応などの分野におけるロボット開発,さらに関心を集めるドローンへの応用,ロボット開発に重要な要素となるレーザー・光技術など,注目するロボットの研究・開発と、アプリケーションという観点からレーザー・光技術の関わりについて解説します。
月刊 OPTRONICS 12 月号の特集は,光技術がもたらすロボット開発の可能性を探ります。医療,農・林業,災害対応などの分野におけるロボット開発,さらに関心を集めるドローンへの応用,ロボット開発に重要な要素となるレーザー・光技術など,注目するロボットの研究・開発と、アプリケーションという観点からレーザー・光技術の関わりについて解説します。  約3年ぶりの大幅改訂!ヘッドアップディスプレイ、プロジェクター、ヘッドランプなど商品化が急加速する「レーザー照明・ディスプレイ」の最新動向が満載です!
約3年ぶりの大幅改訂!ヘッドアップディスプレイ、プロジェクター、ヘッドランプなど商品化が急加速する「レーザー照明・ディスプレイ」の最新動向が満載です! ディスプレイと社会別冊「大型ディスプレイ&デジタルサイネージ総覧2016」の取り扱いを開始しました。
ディスプレイと社会別冊「大型ディスプレイ&デジタルサイネージ総覧2016」の取り扱いを開始しました。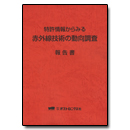 本調査報告書は、赤外線技術解説および赤外線デバイス・応用別の特許調査、その結果をもとに出願人・発明者・国別など様々な角度から分析、さらには中国の特許動向も調査いたしました。赤外線ビジネスの戦略立案に非常に有効な情報源としてご活用いただけます。
本調査報告書は、赤外線技術解説および赤外線デバイス・応用別の特許調査、その結果をもとに出願人・発明者・国別など様々な角度から分析、さらには中国の特許動向も調査いたしました。赤外線ビジネスの戦略立案に非常に有効な情報源としてご活用いただけます。 専門書を読む前に、レーザーや光学への理解を深めるのに最適な一冊。
専門書を読む前に、レーザーや光学への理解を深めるのに最適な一冊。 OSA(Optics Society of America)は,創立100周年を迎えたのを機に,
OSA(Optics Society of America)は,創立100周年を迎えたのを機に,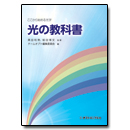 「光学入門」と題する教科書は数多くありますが、初心者の方にとっては、それでも難しいと感じることが多いようです。本書では、高校理科の基礎知識をお持ちの方であれば抵抗なくお読みいただけます。
「光学入門」と題する教科書は数多くありますが、初心者の方にとっては、それでも難しいと感じることが多いようです。本書では、高校理科の基礎知識をお持ちの方であれば抵抗なくお読みいただけます。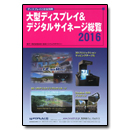 ディスプレイと社会別冊「大型ディスプレイ&デジタルサイネージ総覧2016」の取り扱いを開始しました。
ディスプレイと社会別冊「大型ディスプレイ&デジタルサイネージ総覧2016」の取り扱いを開始しました。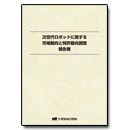
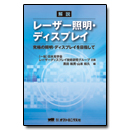 本書は、2010年刊行「解説 レーザーディスプレイ -基礎から応用まで-」を最新の状況を踏まえ大幅改訂し、新たにレーザー照明についての解説を加えたものである。
本書は、2010年刊行「解説 レーザーディスプレイ -基礎から応用まで-」を最新の状況を踏まえ大幅改訂し、新たにレーザー照明についての解説を加えたものである。
 豊富なカラー写真とカラーイラストを通して,教科書だけでは伝わらない光学の基礎とその魅力を紹介。
豊富なカラー写真とカラーイラストを通して,教科書だけでは伝わらない光学の基礎とその魅力を紹介。