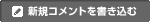書籍
書籍
商品コード:
9784902312829
ひも解くひかり 身近なひかり
販売価格(税込):
3,080
円
ポイント:
30
Pt
谷田貝 豊彦 著
A5判 約170頁
オプトロニクス社
2025年10月27日刊行
第1章 私たちは光をどう理解してきたのか
第2章 波
第3章 光の波 ―光の伝わりと性質―
第4章 鏡・レンズ ―像はどのようにしてできるのか―
第5章 望遠鏡 ―どこまで遠くが見えるのか―
第6章 顕微鏡 ―どこまで細かいものが見えるの―
第7章 光の干渉と回折の展開
本書について
私たちのまわりには、光があふれています。
青い空、鏡に映る自分、写真、通信、生命の営み、そのすべてを支えるのが光のはたらきです。
古代の神話からニュートン、アインシュタインへと受け継がれた「光をめぐる探求」。
本書は、そんな光の本質と歴史、そして現代技術とのつながりを、数式をできるだけ使わずにわかりやすく解説します。
反射・屈折・干渉・回折などの基本原理から、望遠鏡・顕微鏡・ホログラムまで、光の科学の面白さが一冊に。
中高生から大人まで、読むたびに新しい“ひかり”が見えてくる光学入門書です。
<本書の特長>
・身近な光から“科学の本質”へ
日常の光現象を入り口に、反射・屈折・干渉・回折などの基本原理をわかりやすく解説。
・光をめぐる探究の歴史をたどる
古代ギリシャの哲学者、ニュートン、ホイヘンス、アインシュタイン……
人類の知がどのように光を理解してきたかを物語として紹介。
・現代技術につながる応用まで
望遠鏡・顕微鏡・ホログラム・干渉計など、
光学が今も最先端科学を支えることを実感できる内容。
詳細目次
はじめに
第1章 私たちは光をどう理解してきたのか
1.1 太陽の恵み
1.2 光とは何か
1.2.1 古代の鏡とレンズ
1.3 古代ギリシャの哲学者たち
1.3.1 なぜ見えるのか
1.3.2 光の伝わり方
1.3.3 光は粒か波か
1.4 イスラームの科学
1.4.1 古代ギリシャからルネッサンスへの橋渡し
1.4.2 アル=ハイサム ―最初の科学者
1.5 東洋では
1.5.1 墨子と淮南子
1.6 ルネッサンスから近代に
1.7 望遠鏡と顕微鏡の発明
1.8 ニュートンの時代
1.9 ホイヘンスの波動説
1.10 近代科学の夜明け
1.10.1 ファラディーとマックスウエル
1.11 アインシュタイン登場
1.12 光の時代
第2章 波
2.1 波とは
2.1.1 正弦波
2.1.2 波のエネルギー
2.2 横波と縦波
2.3 波面と波の方向(光線)
2.4 波の重なり
2.4.1 うなり ―振動数が異なる波の重ね合わせ―
2.4.2 波連
2.4.3 群速度
2.5 波の広がり
2.5.1 ホイヘンスによる説明
2.6 波の反射と屈折
2.6.1 ホイヘンスの原理による反射と屈折
2.6.2 境界面における波の連続性
2.6.3 「光は寄り道しない」 ―フェルマーの原理―
2.6.4 波は最短時間経路を知っているのか
第3章 光の波 ―光の伝わりと性質―
3.1 光の波とは
3.1.1 光速度
3.2 光の干渉
3.2.1 ヤングの実験
3.2.2 多層膜
3.2.3 最も簡単な反射防止膜
3.2.4 干渉する光と干渉しない光
3.3 光の回折
3.3.1 フレネルやキルヒホッフによる回折の説明
3.3.2 アポロ11 号の反射鏡
3.3.3 なぜ星は星形に見えるのか
3.4 屈折率とスネルの法則
3.4.1 全反射
3.4.2 完全無反射
3.4.3 反射率と透過率
3.5 屈折率
3.5.1 屈折率とは
3.5.2 屈折率と原子★
3.5.3 なぜ光は媒質中で遅くなるのか
3.5.4 なぜ光の波長は媒質中では短くなるのか
3.5.5 光はなぜ屈折するのか
3.6 光の速さ
3.6.1 レーマーによる測定
3.6.2 フィゾーによる測定
3.7 光速度の定義
3.8 光を伝える媒質
3.8.1 マイケルソン・モーレイの実験
3.8.2 光速不変の原理
3.8.3 特殊相対性理論★
3.8.4 光のエネルギーと運動量★
3.8.5 反射・屈折と運動量と光の圧力★
3.9 光の偏り
3.9.1 偏光
3.9.2 偏光をつくる
3.9.3 反射と偏光
3.9.4 偏光をつくる物質
3.9.5 ジュエリーバブル
3.10 空からくる光 ―光の散乱―
3.10.1 虹
3.10.2 ハロー
3.10.3 たばこの煙、雲の白
3.10.4 空の青、夕日の赤
3.11 火星の青い夕日
3.12 空の偏光
3.13 バイキングのコンパス
3.14 光害
第4章 鏡・レンズ ―像はどのようにしてできるのか―
4.1 光線の反射
4.1.1 平面鏡
4.1.2 凹面鏡と凸面鏡
4.1.3 魔鏡
4.2 近軸光線
4.3 プリズム
4.4 球面での屈折
4.5 レンズ
4.5.1 薄肉レンズ
4.5.2 作図による結像の説明
4.5.3 薄肉レンズの組み合わせ
4.5.4 蝴蝶杯
4.5.5 厚肉レンズ
4.5.6 レンズの倍率
4.5.7 レンズの焦点像
4.5.8 分解能
4.6 収差
4.6.1 収差とは
4.6.2 収差の補正
第5章 望遠鏡 ―どこまで遠くが見えるのか―
5.1 ガリレイ式望遠鏡
5.2 ケプラー式望遠鏡
5.3 反射望遠鏡
5.4 対物レンズの色収差
5.5 大型反射望遠鏡
5.6 双眼鏡
第6章 顕微鏡 ―どこまで細かいものが見えるの―
6.1 虫メガネ
6.2 顕微鏡
6.3 レーウェンフックの単レンズ顕微鏡
6.4 新しい顕微鏡
6.4.1 共焦点顕微鏡
6.4.2 蛍光顕微鏡
?6.4.3 超解像顕微鏡
第7章 光の干渉と回折の展開
7.1 長さと形を測る干渉計
7.1.1 二光束干渉計
7.1.2 干渉縞の自動解析
7.2 光干渉断層計(OCT) ―網膜の断面を見る―
7.3 超高感度干渉計測
7.3.1 星の大きさを測る
7.3.2 重力波を捕らえる
7.4 格子を通る光
7.4.1 回折格子
7.4.2 構造色
7.5 波を集める ―像を作る格子―
7.6 立体像が見える
7.6.1 ホログラム
7.6.2 点物体のホログラム
7.6.3 立体的な物体のホログラム
7.6.4 ホログラムの応用
深く学ぶために
索引